国立研究開発法人 国立長寿医療研究センターを訪問

令和7年7月24日、愛知県の国立研究開発法人 国立長寿医療研究センターを訪問してきました。国立長寿医療研究センターでは、心と体の自立を促進し健康長寿社会構築に貢献し、エビデンス(科学的根拠)にもとづき、高齢者自立阻害の2大要因:認知症、運動器疾患・虚弱(フレイル)の課題解決のために取り組んでいます。
長寿研研究所長の櫻井孝先生から研究センターの取り組み、とりわけ認知症の一歩手前の状態とされる軽度認知障害(MCI)について、レクチャーを受け、早期に発見し適切な対策をとれば、MCIを改善したり、認知症の発症を予防できる具体的な取り組みを見学させて頂きました。




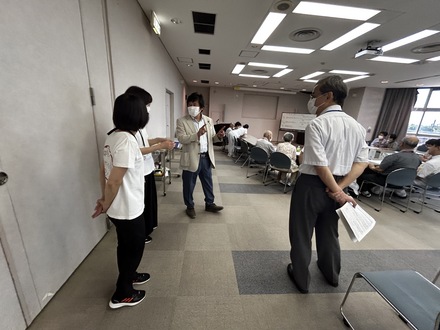
1.MCI(軽度認知障害)への実証的取り組み
櫻井孝先生は、「もの忘れセンター」を拠点に、MCI(軽度認知障害)と診断された高齢者を対象に、認知機能の進行抑制を目的とした多因子介入プログラムの研究を推進しています。
認知症リスクを抱える高齢者(65〜85歳、NCGG-FATでドメイン低下がある者=MCI)を対象に、生活習慣病管理、運動指導、栄養指導、認知トレーニング、社会参加支援などを組み合わせた多因子介入により、認知機能低下の抑制効果とそのメカニズムを明らかにするJ-MINT研究の概要は、全国5施設(国立長寿医療研究センター、名古屋大学、名古屋市立大学、藤田医科大学、東京都健康長寿医療センター)による多施設共同・オープンラベルのランダム化比較試験(RCT)。対象者約500名(介入群250名/対照群250名)に対し18か月の介入を実施しているとのことです。18か月間における認知機能コンポジットスコアの変化量、副次的評価として6・12ヶ月時点での認知テスト変化、血液バイオマーカー、ADL・フレイル指標、頭部画像所見なども評価しています。
進捗と成果としては、COVID-19禍の影響による中断もありましたが、約70%以上の参加率を維持した運動教室に参加した群では、認知機能の維持・向上に有意な効果が確認されました。また、血液バイオマーカー、オミックス解析、脳画像を駆使することで、介入による認知機能抑制の生理学的機序も検討されています。そして、フォローアップとして終了後も毎年追跡調査を継続し、中長期的な認知症発症抑制効果の検証が継続されています。
2.J-MINT研究の意義と特色
国際的先行研究との比較すると、フィンランド発のFINGER研究(多因子介入による認知機能改善)は、世界標準となるエビデンスを示しましたが、文化や生活習慣が異なる名、日本国内でも同様の成果が得られるのかを検証する必要がありました。J-MINT研究は、日本版FINGERとして、国立長寿医療研究センターを中心に、地域文化や生活習慣に即した介入設計を行った点で特色があります。そして、介入群と対照群との比較によって、どの程度認知機能の低下を抑制できるかを評価。さらに、バイオマーカーや画像解析により「なぜ介入が効くのか」を明らかにし、理論的な裏付けも得ています。
3.社会実装へのアプローチ
国立長寿医療研究センターでは、エビデンス構築のみでなく、社会実装に向けた具体的ステップも主導しています。それが、地域版J#8209MINTプログラム開発であり、まさに2025年7月に、「地域版J-MINTプログラム」を開発・普及へ向けた取り組みを本格化しました。民間企業(J-MINT認定推進機構株式会社、SOMPOホールディングス、コナミスポーツなど)と連携し、質の高い介入プログラムを教室形式で提供する体制を構築しています。
プログラム内容:週1回・約20人グループでの有酸素運動+筋力トレーニング、認知二重課題運動、栄養指導、認知トレーニング、ライフスタイル改善や社会参加を促進するグループワークなど多面的介入。認定制度による品質保証するため、J-MINTパートナー制度として、自治体や事業者を「プログラム提供主体」として認定し、全国展開を支援。J-MINTインストラクター制度でも、教室で高品質な実施を担保するインストラクターを育成・認証する仕組みを構築します。
今後の研究・展開計画では、2026〜2027年度に、自治体を対象とした「地域版J-MINTプログラム」の有効性を検証する研究を実施予定されています。参加自治体を募集中であり、研究費負担や専門支援を提供する仕組みも整備されています。また、厚生労働省の支援事業(中小企業イノベーション創出推進事業)を通じ、リアルワールドデータやAIシステムを用いた早期発見・介入システムの構築にも乗り出しています。
今後、MCI=認知症予備群に対する介入として、科学的厳密性と国内事情への適合性を両立した大規模RCTを実施されてくると思います。介入の効果だけでなく、作用メカニズムを明らかにすることで、次世代のサービス開発やAI導入などにつなげています。社会実装の道筋では、単なる研究成果では終わらず、教室運営、認定制度、自治体連携、民間提供体制などを包括的に整備し、「いつでも誰でもどこでも受けられる」サービスモデルを構築する予定です。そのために、自治体協力や事業者認定を通じ、全国展開を目指すことで、高齢者が住む地域にかかわらず、エビデンスに基づいた認知症予防が可能となる展望があります。
国立長寿医療研究センターの取り組みは、軽度認知障害の進行抑制に向けたエビデンス構築から、その社会実装に至る包括的な展開を描いており、今後の日本における認知症予防政策や地域介入のモデルとなる可能性を秘めていると思いました。
 |
その他令和7年活動報告はこちらから>>
Copyright © Since 2005 Kouzakisatoshi.com. All Rights Reserved.
|